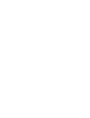張 楨林(ちょう ていりん)
2002年華東理工大学コンピュータ科学専攻を卒業。
東軟グループ(Neusoft)、ビステオン・ジャパン株式会社(Visteon)、株式会社ヴァレオジャパン(Valeo)、コンチネンタル・オートモーティブ(Continental Automotive)にて、システムエンジニアリーダー、プログラムマネージャーなどを歴任。現在は、オランダ発のTomTomにて、自動車向けGPSナビゲーションユニットの開発・販売などを担当。長年にわたって、日系企業・外資系企業にて多国籍のチームと共に研究開発、生産販売に従事する。